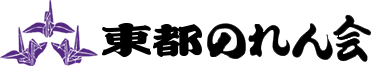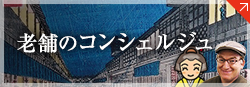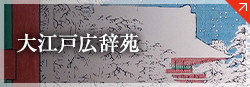| 西暦 |
江戸年号 |
創業年 老舗名 |
歴史・文化情報 |
| 1500~ |
|
室町時代後期 とらや |
| 1543年: |
鉄砲伝来 |
| 1549年: |
キリスト教伝来 |
| 1560年: |
桶狭間の戦い |
|
| 1590 |
|
天正18年 伊場仙 |
| 1590年: |
徳川家康、江戸城に入る。豊臣秀吉、全国統一。継飛脚始まる |
|
| 1596~ |
慶長(けいちょう)年間 |
慶長元年 豊島屋本店 |
| 1596年: |
長崎で26聖人殉教 |
| 1597年: |
慶長の役 |
| 1601年: |
東海道に53宿を確定 |
|
1603
【江戸】 |
慶長8年(江戸開府) |
|
|
| 1615~ |
元和(げんな)年間 |
|
| 1615年: |
大阪夏の陣 |
| 1617年: |
吉原遊郭の開設許可 |
| 1619年: |
菱垣廻船創設 |
| 1323年: |
将軍、家光 |
|
| 1624~ |
寛永(かんえい)年間 |
寛永2年 やげん堀中島商店 |
| 1625年: |
上野寛永寺創建 |
| 1635年: |
参勤交代始まる |
| 1637年: |
島原の乱 |
| 1639年: |
ポルトガル船の来航禁止(鎖国の完成) |
|
| 1648~ |
慶安(けいあん)年間 |
|
|
| 1652~ |
承応(じょうおう)年間 |
|
|
| 1655~ |
明暦(めいれき)年間 |
|
|
| 1658~ |
万治(まんじ)年間 |
|
| 1659年: |
江戸城本丸竣工(天守閣は再建されず) |
|
| 1660~ |
寛文(かんぶん)年間 |
|
|
| 1673~ |
延宝(えいほう)年間 |
|
| 1673年: |
越後屋呉服店創業。市川団十郎、江戸に歌舞伎を確立 |
| 1674年: |
関孝和『発微算法』 |
| 1680年: |
将軍、綱吉 |
|
| 1681~ |
天和(てんな)年間 |
|
| 1682年: |
井原西鶴『好色一代男』。江戸大火(お七の火事) |
|
| 1684~ |
貞享(じょうきょう)年間 |
|
| 1685年: |
綱吉、最初の生類憐みの令を初めて発す(廃止は1709年) |
|
| 1688~ |
元禄(げんろく)年間 |
元禄元年 神茂
元禄元年 ちくま味噌
元禄02年 黒江屋
元禄03年 山本山
元禄04年 笹乃雪
元禄12年 にんべん
元禄年間 秋色庵大坂家 |
| 1688年: |
大阪堂島に米穀取引所を設立 |
| 1689年: |
宮崎友禅、友禅染を創始。松尾芭蕉『奥の細道』 |
| 1693年頃: |
菱川師宣「見返美人図」 |
| 1695年: |
荻原重秀、悪貨を発行 |
| 1698年: |
柳沢吉保、老中筆頭になる。江戸大火(勅額火事) |
| 1703年: |
赤穂浪士討ち入り。尾形光琳「燕子鼻図屏風」 |
|
| 1704〜 |
宝永(ほうえい)年間 |
宝永元年 日本橋さるや |
| 1705年: |
伊勢おかげ参り362万人 |
| 1707年: |
富士山噴火 |
| 1709年: |
東大寺大仏殿再建 |
| 1709年: |
将軍、家宣。新井白石ら登用 |
|
| 1711~ |
正徳(しょうとく)年間 |
正徳元年 吉徳 |
| 1713年: |
将軍、家継 |
| 1714年: |
江島事件。貨幣を改鋳し、品質を戻す |
|
| 1716~ |
享保(きょうほう)年間 |
享保2年 長命寺桜もち
享保3年 江戸屋 |
| 1716年: |
将軍、吉宗。「享保の改革」 |
| 1717年: |
大岡忠相(越前守)、町奉行に |
| 1720年: |
江戸町火消いろは47組創設 |
| 1720年: |
近松門左衛門『心中 天網島』 |
| 1732年: |
享保の大飢饉。1733年:江戸で打ちこわし |
|
| 1736~ |
元文(がんぶん)年間 |
|
|
| 1741~ |
寛保(かんぽう)年間 |
|
| 1741年: |
農民の逃散、強訴禁止。オランダ商館を出島へ移転(鎖国完成) |
|
| 1744~ |
延享(えんきょう)年間 |
|
|
| 1751~ |
宝暦(ほうれき)年間 |
|
| 1755年: |
宝暦の大飢饉 |
| 1757年: |
関東大洪水、東北飢饉 |
| 1760年: |
江戸大火。賀茂真淵『万葉考』。将軍、家治 |
|
| 1764~ |
明和(めいわ)年間 |
|
| 1765年: |
鈴木春信、錦絵を開始。円山応挙『雪松図屏風』 |
| 1770年: |
諸国に大かんばつ |
|
| 1772~ |
安永(あんえい)年間 |
安永元年 大野屋總本店 |
| 1772年: |
田沼意次、老中となる |
| 1774年: |
杉田玄白ら『解体新書』 |
| 1776年: |
平賀源内、エレキテル完成。アメリカ独立宣言 |
|
| 1781~ |
天明(てんめい)年間 |
天明2年 新橋玉木屋
天明3年 うぶけや |
| 1782年: |
天明の大飢饉(~87) |
| 1783年: |
浅間山大噴火 |
| 1786年: |
将軍、家斉 |
| 1787年: |
松平定信による寛政の改革、倹約令を出す |
|
| 1789~ |
寛政(かんせい)年間 |
寛政元年 総本家更科堀井
寛政4年 安田松慶堂 |
| 1789年: |
囲い米の制 |
| 1790年: |
人足寄場を向島に設置 |
| 1791年: |
江戸銭湯、男女混浴の禁止 |
| 1799年: |
米価騰貴のため江戸・大阪で打ち壊し |
|
| 1801~ |
享和(きょうわ)年間 |
享和元年 駒形どぜう |
| 1801年: |
伊能忠敬、全国の測量開始(1821年『大日本沿海與地全図』完成) |
| 1802年: |
諸国大洪水。十返舎一九『東海道中膝栗毛・初編』 |
|
| 1804~ |
文化(ぶんか)年間 |
文化元年 MATSUZAKI SHOTEN
(旧:銀座松崎煎餅)
文化2年 亀戸船橋屋
明神下神田川本店
文化3年 榛原 |
| 1804年: |
ナポレオン皇帝即位 |
| 1808年: |
間宮林蔵、樺太探検 |
| 1810年: |
大阪町人に御用金を命ず |
| 1811年: |
式亭三馬『浮世床』初編 |
| 1814年: |
滝沢馬琴『南総里見八犬伝』第1輯刊 |
|
| 1818~ |
文政(ぶんせい)年間 |
文政元年 榮太樓總本鋪
文政2年 羽二重団子
文化文政頃 前川 |
| 1819年: |
小林一茶『おらが春』 |
| 1822年: |
西国にコレラ流行 |
| 1828年: |
シーボルト事件で追放(来日は1823年) |
| 1829年: |
江戸大火。葛飾北斎「富嶽三十六景」 |
|
| 1830~ |
天保(てんぽう)年間 |
天保元年 いせ源
天保元年 白木屋傳兵衛
天保05年 千疋屋総本店
天保13年 竺仙 |
| 1830年: |
伊勢おかげ参り(486万人) |
| 1833年: |
天保の大飢饉(~39)。歌川広重「東海道五十三次」 |
| 1837年: |
大塩平八郎の乱。将軍、家慶 |
| 1840年~ |
アヘン戦争 |
| 1841年: |
水野忠邦による天保の改革で倹約令 |
|
| 1844~ |
弘化(こうか)年間 |
|
|
| 1848~ |
嘉永(かえい)年間 |
嘉永2年 山本海苔店
嘉永3年 日本橋弁松総本店
嘉永3年 梅花亭 |
| 1848年: |
フランス二月革命 |
| 1849年: |
アメリカでゴールドラッシュ |
| 1851年: |
ジョン万次郎、米国から帰国。島津斉彬精錬所設立 |
| 1853年: |
将軍、家定。ペリー浦賀来航 |
|
| 1854~ |
安政(あんせい)年間 |
安政元年 梅園
安政元年 吉野屋商店
安政6年 蓮玉庵 |
| 1854年: |
米英露と和親条約締結 |
| 1855年: |
江戸大地震。日蘭和親条約 |
| 1856年: |
吉田松陰、松下村塾を開く |
| 1858年: |
将軍、家茂。江戸にコレラ大流行(死者3万人) |
| 1858~ |
安政の大獄 |
| 1859年: |
横浜、長崎、函館を開港 |
|
| 1860 |
万延(まんえん)年間 |
|
| 1860年: |
勝海舟ら咸臨丸で太平洋横断。桜田門外の変(井伊直弼暗殺) |
|
| 1861~ |
文久(ぶんきゅう)年間 |
文久元年 宮本卯之助商店 |
| 1861年: |
皇女和宮、家茂に降嫁。アメリカ南北戦争(~65) |
|
生麦事件 |
| 1963年: |
薩英戦争 |
|
| 1864 |
元治(げんじ)年間 |
元治元年 菊寿堂いせ辰 |
| 1864年: |
池田屋事件(新撰組、尊皇攘夷志士を襲う)。第1次長州征討 |
|
| 1865~ |
慶応(けいおう)年間 |
慶応元年 豆源
江戸末期 言問団子
江戸末期 竹葉亭 |
| 1866年: |
薩長連合なる。将軍、慶喜。諸国凶作、各地に一揆、打ちこわし |
| 1867年: |
兵庫開港勅許。徳川慶喜、大政奉還。王政復古の大号令。「ええじゃないか」始まる。坂本龍馬・中岡慎太郎、殺される |
|
1868~
【明治】 |
|
|
|
明治2年 木村屋總本店
明治2年 室町砂場
|
| 1869年: |
東京遷都。戊辰戦争。版籍奉還。全国に農民一揆(世直し騒動)続発。京浜間電信開通 |
|
| 明治3年 中清 |
| 1870年: |
平民に苗字許す。神道、国教に。日本初の日刊新聞「横浜毎日新聞」創刊 |
|
明治5年 両国橋鳥安
明治5年 上野精養軒 |
| 1872年: |
太陽暦採用(明治5年12月3日が6年1月1日)。富岡製糸場設立。新橋・横浜鉄道開通 |
| 1873年: |
日本初の銀行・第一国立銀行開業 |
|
| 明治10年 志乃多寿司総本店 |
| 1877年: |
西南戦争。東京大学開設 |
| 1879年: |
エジソン電灯発明 |
|
明治13年 かんだやぶそば
明治32年 ホテル龍名館東京 |
| 1880年: |
林広守『君が代』作曲 |
| 1883年: |
鹿鳴館落成 |
| 1889年: |
大日本帝国憲法発布 |
|